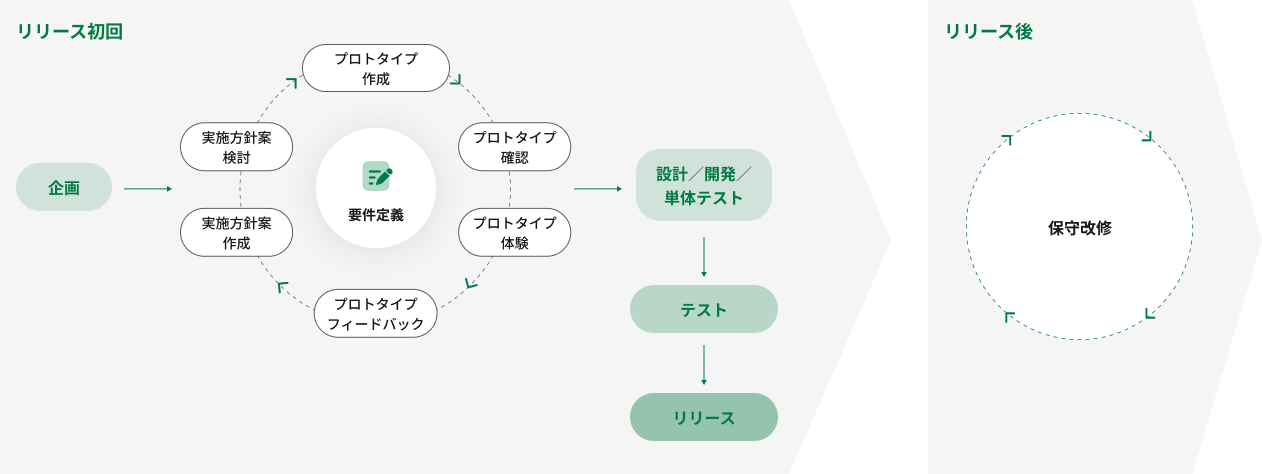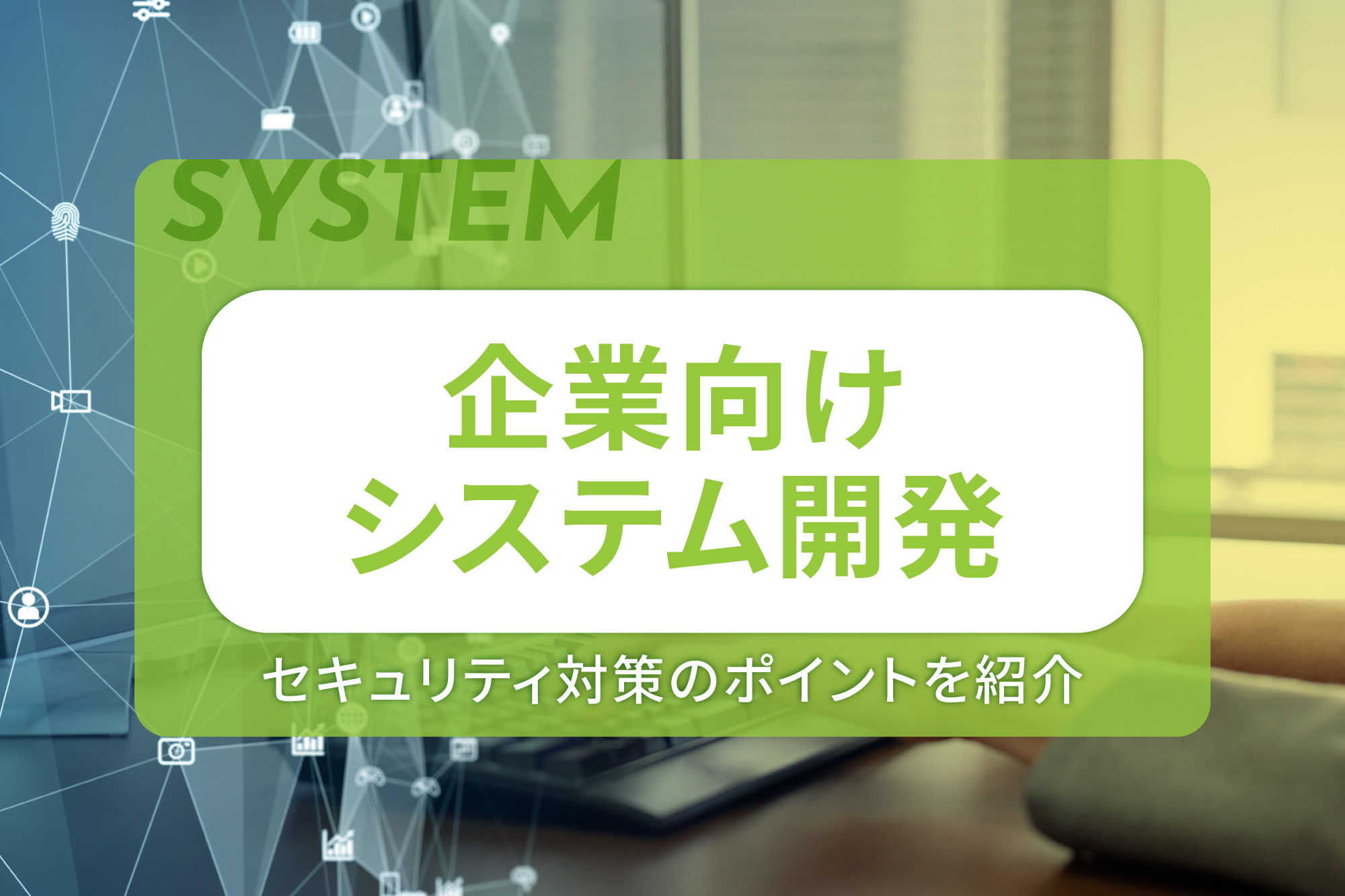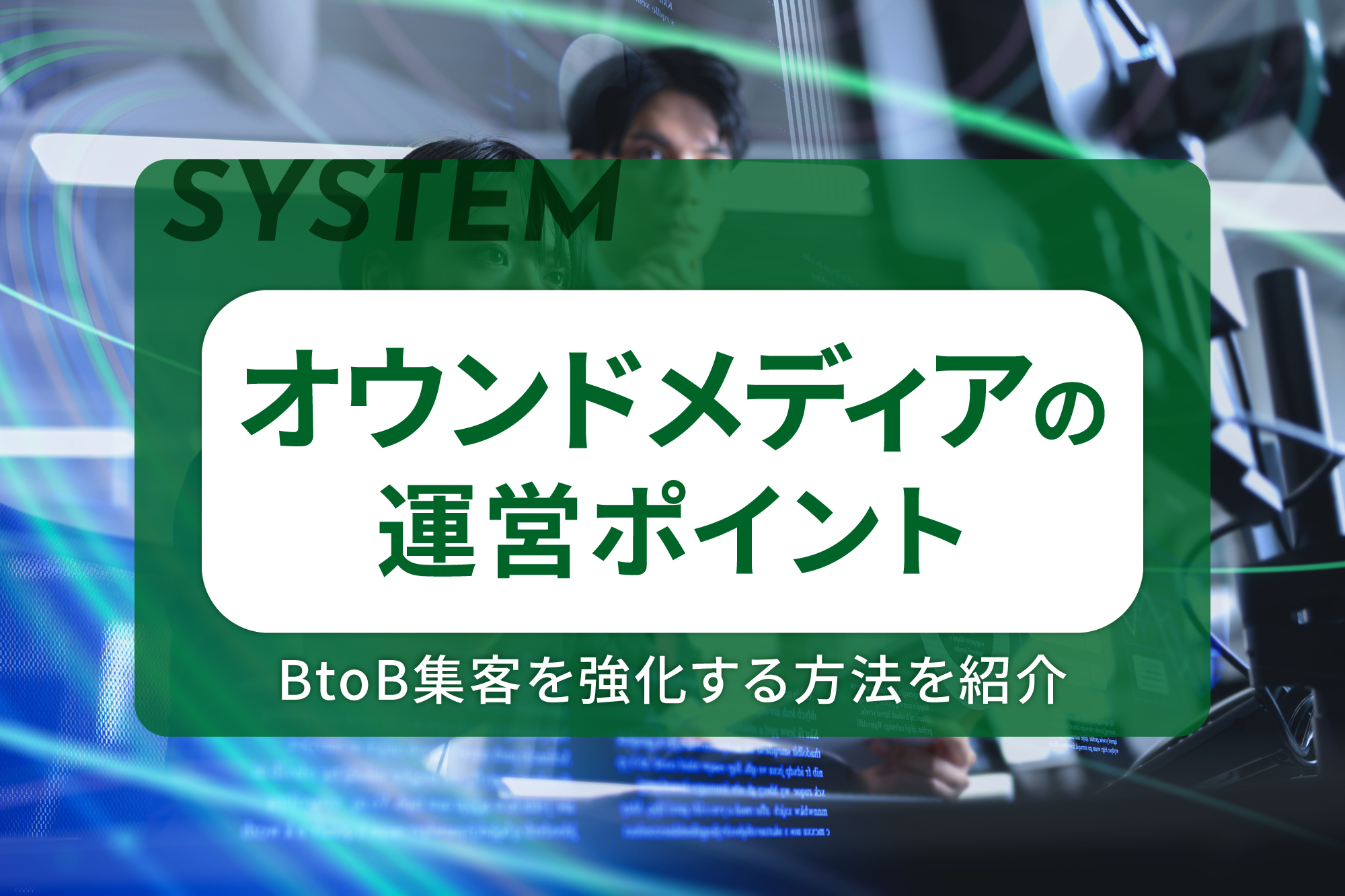マンション管理組合の運営は、住民の高齢化やライフスタイルの変化により、役員のなり手不足という課題に直面しています。また、建物の老朽化が進むにつれて大規模修繕などの専門的な判断が求められ、運営の負担は増す一方です。
そこで注目されているのが、マンション管理の専門家に運営を委託する「第三者管理方式」です。専門家の知見を活用することで、管理組合の運営を安定させられます。
本記事では、第三者管理方式が注目される社会的な背景や、導入を検討すべき具体的なケース、そして主な依頼先について解説します。
グローバルスタンダード!?第三者管理方式に注目が集まる理由

第三者管理方式とは、マンション管理組合の運営実務を、マンション管理士などの外部専門家に委託する仕組みです。役員のなり手不足や住民の高齢化など、多くのマンションが抱える構造的な課題を解決する手段として注目されています。
本章では、なぜ今、第三者管理方式が必要とされているのか、その背景にある主な5つの理由を解説します。
マンション標準管理規約が改正されたから
第三者管理方式が広く検討されるようになったきっかけは、国の指針である「マンション標準管理規約」が改正されたことです。規約改正により、従来は曖昧だった外部の専門家(マンション管理士など)が、管理組合の「理事」や「監事」、あるいは理事会に代わる「管理者」として就任できることが公式に認められました。
国が具体的なパターンを示したことで、管理組合が総会で合意形成を図る際の明確な根拠が生まれ、導入への道筋が整ったのです。規約改正による法的な後ろ盾が、普及を後押ししています。
居住者が高齢化しているから
多くのマンションで、新築時から住み続ける方の高齢化が進んでいます。役員に選ばれても、総会や理事会への出席といった活動が身体的に負担となるケースが増加しました。さらに、会計や法律、建築に関する専門知識が求められる場面も多く、精神的なプレッシャーも少なくありません。
このような状況で責任ある役職を担うことは難しく、安心して管理を任せられる専門家の存在が求められています。
担い手が不足しているから
ライフスタイルの多様化も、担い手不足を引き起こす一因です。共働き世帯が増加し、日中の理事会活動に参加できる人が限られるようになりました。また、「役員の責任を負いたくない」「住民間のトラブルに関わりたくない」といった理由から、役員就任を敬遠する人も少なくありません。
その結果、一部の意欲ある人に負担が集中し、該当者が退任すると運営が立ち行かなくなるという悪循環に陥りがちです。このような担い手不足という構造的な問題を解決する手段として、第三者管理方式が選ばれています。
マンションの老朽化が進んでいるから
建物の老朽化も、専門家による管理運営が必要とされる理由です。築年数が経過したマンションでは、大規模修繕工事や将来の建て替えといった、専門性が高く複雑な課題に直面します。
工事業者の選定や工事費用の交渉、修繕積立金の改定など、一つひとつの意思決定がマンションの資産価値に影響します。大規模修繕などの重要事項を専門知識のない住民だけで判断するのは困難であり、管理不全に陥るリスクも高まるのです。
投資用マンションが増加しているから
近年、自身が住むためではなく、投資目的でマンションを所有する区分所有者が増えています。投資用マンションの所有者は、その物件に住んでいないことがほとんどです。遠隔地に居住しているため、物理的に理事会へ参加できません。
また、マンション管理そのものへの関心が低い傾向にあり、役員の候補者となり得る人が少なくなります。そのため、居住者だけで運営を担うのは厳しく、第三者管理方式の導入が検討されるのです。
第三者管理方式を導入すべきケース・すべきでないケース
第三者管理方式には多くのメリットがありますが、すべてのマンションに適した解決策ではありません。自分たちのマンションの状況を客観的に見極め、導入が本当に必要かどうかを慎重に判断することが重要です。
本章では、導入を積極的に検討すべきケースと、そうでないケースの具体例を解説します。
第三者管理方式を導入すべきケース
理事会の役員候補者が見つからない、あるいは理事が長期間固定化して一部の人に負担が集中している状況は、導入を検討すべき典型的なケースです。
理事会が機能不全に陥る状況は、適切なマンション管理を妨げる原因になります。また、投資目的で所有する人が多く、運営の担い手そのものを見つけるのが難しいマンションも同様です。専門家が運営を代行することで、安定した管理体制を再構築し、資産価値の維持が期待できます。
第三者管理方式を導入すべきでないケース
一方で、住民の間に自主的にマンションを運営しようという意識が高い場合は、導入を急ぐ必要はありません。住民間のコミュニケーションが活発で、協力して管理組合の活動を行える体制が整っているなら、現状の運営方法を維持する方が望ましいでしょう。
また、専門家への報酬などのコスト負担について住民の合意が得られない場合、無理に導入を進めると新たなトラブルの原因になる可能性があります。
第三者管理方式の依頼先
第三者管理方式の導入を決定したら、次に重要なのが「誰に運営を委託するか」という依頼先の選定です。主な選択肢は「外部の専門家」と「管理会社」の2つがあり、それぞれにメリットと注意すべき点が存在します。
マンションの将来を左右する重要な判断であるため、両者の違いを正確に理解し、自分たちのコミュニティに合ったパートナーを見極めることが重要です。
外部の専門家
一つ目の選択肢は、マンション管理士や弁護士といった、特定の企業に所属しない独立した専門家です。専門家に依頼するメリットは、「中立性」にあります。管理会社とは利害関係がないため、管理組合の利益を最優先に考えた客観的な判断が期待できます。
例えば、管理会社から提出される業務報告や見積もりを厳しくチェックしたり、大規模修繕工事の業者選定を公平な立場で進めたりすることが可能です。専門的な知識と第三者の視点を活かし、管理組合の頼れる相談役として運営をサポートします。
管理会社
もう一つの選択肢は、日常の管理業務を委託している管理会社です。既にマンションの設備や住民の状況を詳しく把握しているため、現状からの引き継ぎがスムーズに進む利点があります。
しかし、管理会社に委託する場合、注意すべきなのが「利益相反」のリスクです。管理会社が管理者として強い権限を持つことで、自社の利益を優先し、割高な工事契約を結んだり、不要なサービスを追加したりする懸念があります。
このようなリスクを回避するためには、複数の監事を置いてチェック機能を強化したり、外部の専門家による監査を定期的に導入したりするなど、厳格な監視体制の構築が不可欠です。
状況に応じて第三者管理方式への移行を検討しよう!
第三者管理方式は、役員のなり手不足や住民の高齢化といった課題を解決する手段です。ただし、専門家への報酬が発生するなどの注意点もあるため、自分たちのマンションの状況を見極めて慎重に導入を判断する必要があります。
理事会役員の負担を根本から解消したい場合は、株式会社SPの「PROTHIRD」を選択肢の一つとして検討できます。PROTHIRDは、三菱UFJ信託銀行の専門チームが理事会業務そのものを代行するため、役員の選出が不要です。ご自身のマンションに合った運営方法を検討するために、まずは一度相談してみてはいかがでしょうか。