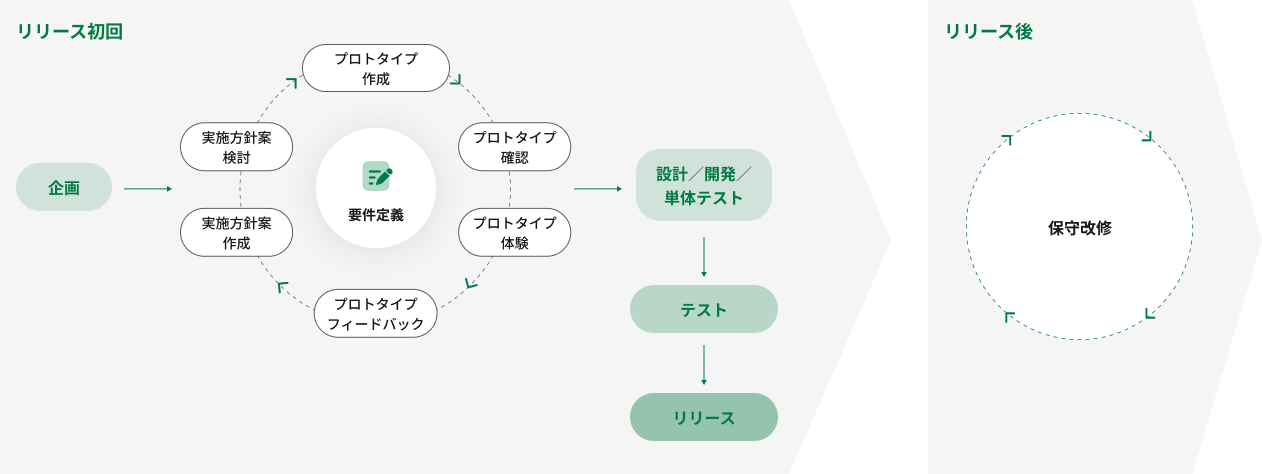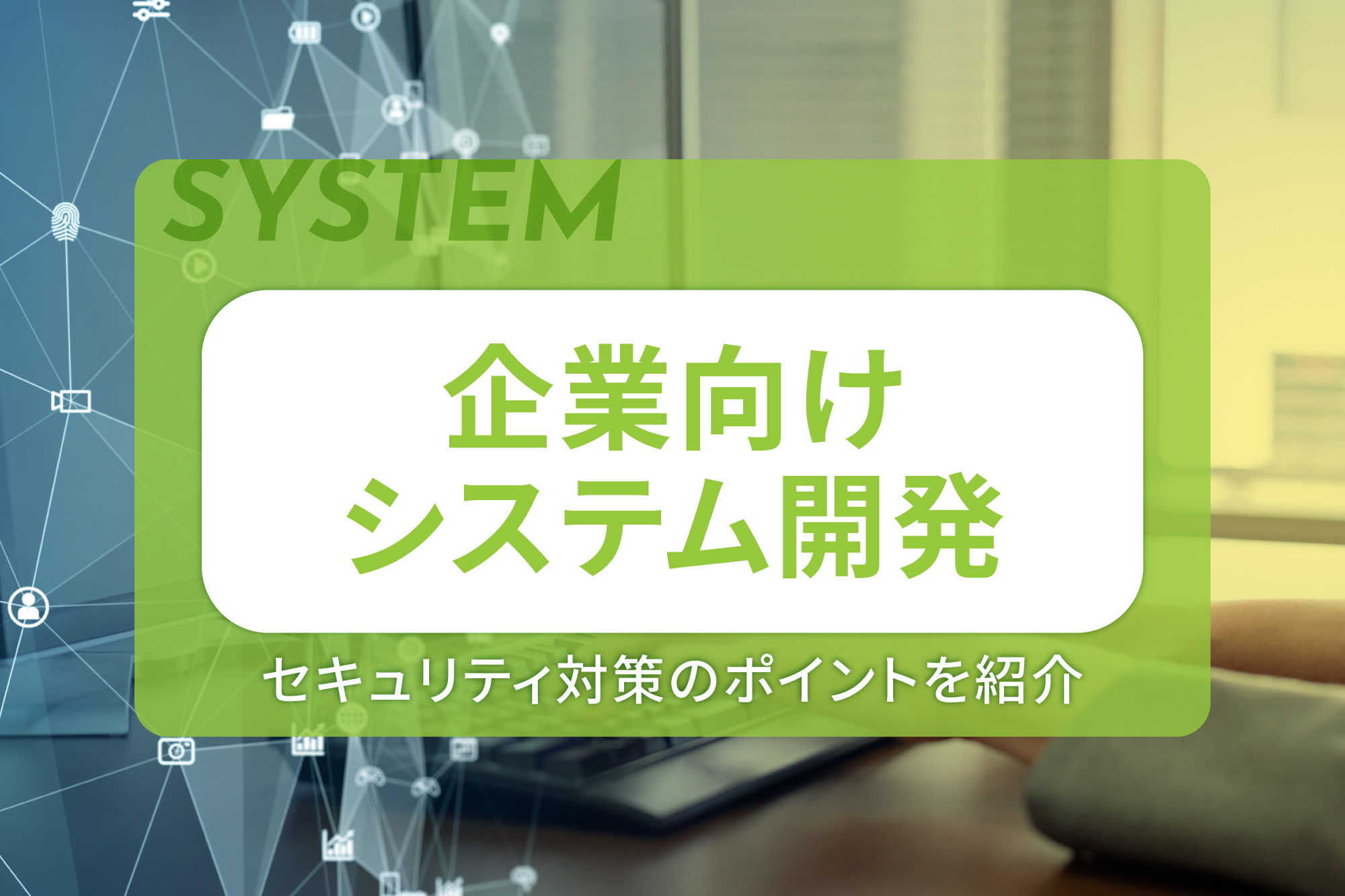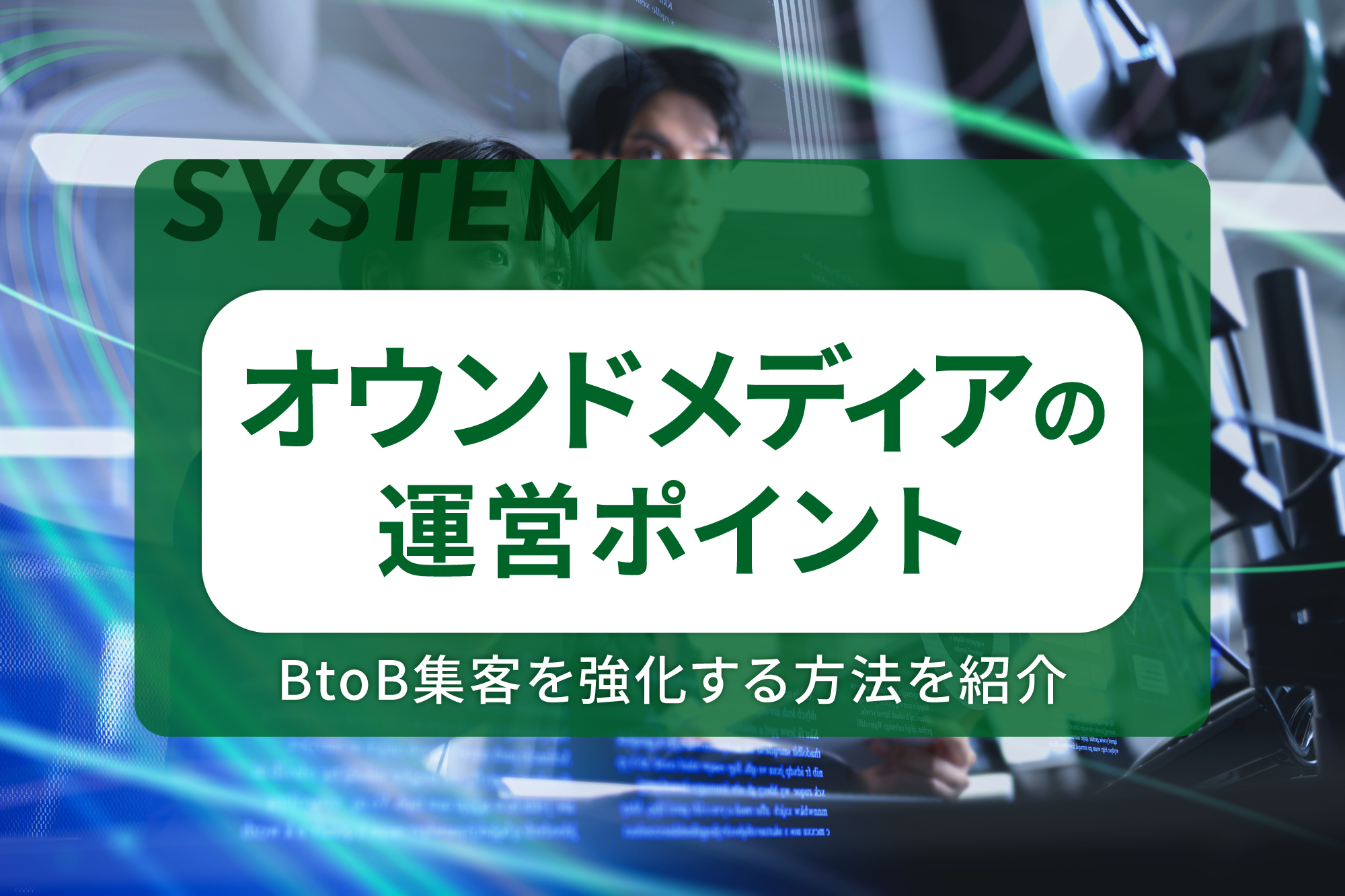社内で複数のシステムを利用していると、データの手入力や転記作業に多くの時間がかかります。このような作業は、業務の非効率化や入力ミスを招く原因にもなります。
そこで注目されているのが、異なるシステム同士をつなぐ「API連携」です。API連携を活用することで、システム間のデータ共有を自動化し、業務プロセスを大きく改善できます。
本記事では、API連携の基本的な仕組みからメリット、具体的な実装方法、活用事例までを分かりやすく解説します。
API連携とは?
API連携とは、異なるソフトウェア同士が持つ機能やデータを、互いに利用できるようにする仕組みです。外部のサービスと連携することで、自社のシステムに新しい機能を追加したり、業務を自動化したりすることが可能です。ビジネスの可能性を広げる技術として、多くの企業で活用が進んでいます。
以下で、API連携の基本的な仕組みや導入メリットについて詳しく解説します。
API連携の仕組み
API連携の仕組みは、プログラムからの「リクエスト(要求)」と、それに対する「レスポンス(応答)」で成り立っています。
まず、連携したい側のシステムが、APIを通じて「このデータが欲しい」「この機能を実行してほしい」といった要求を送ります。要求を受け取ったAPIの提供元システムが内容を処理し、結果を返すという流れです。
この一連のやり取りは、事前に定められたルールに従って自動的に行われるため、異なるソフトウェア同士でもスムーズに機能します。
API連携を活用するメリット
API連携を活用するメリットは、開発コストを大幅に削減できる点です。認証や決済といった機能をゼロから開発する必要がなくなり、開発期間と費用を抑えられます。
また、異なるシステム間のデータ連携が自動化されるため、手作業が減り業務効率が向上します。外部の便利な機能を自社サービスに組み込むことで、顧客満足度を高める効果も期待できるでしょう。セキュリティレベルが高い外部の認証機能を利用し、自社の安全性を強化することも可能です。
API連携を実装する方法
API連携を自社システムに実装するには、いくつかの手順を踏む必要があります。実装には専門知識が求められる場合もありますが、基本的な流れは同様です。以下で、API連携を実装するための具体的なステップを解説します。
目的を明確にする
API連携を実装する最初のステップは、導入目的を具体的に設定することです。「なぜAPI連携を行うのか」「連携によってどの業務課題を解決したいのか」を明確にします。
例えば、「会計ソフトと銀行口座を連携させて経理業務を効率化する」「SNSアカウントでのログイン機能を導入し、顧客の利便性を向上させる」といった目的が考えられます。目的がはっきりすることで、連携すべきシステムや必要な機能が定まり、数あるAPIの中から自社に適したものを選びやすくなるでしょう。
API提供元にユーザー登録する
利用したいAPIが決まったら、次にそのAPIを提供しているサービスの公式サイトでユーザー登録を行います。
登録の際には、サービスの利用規約やAPIの仕様書、料金体系などを十分に確認することが重要です。特に、データの取り扱いやセキュリティに関する規約は念入りにチェックしましょう。
提供元によっては、登録情報をもとにした審査が行われることもあります。この審査は、APIの利用が提供元の定める基準を満たしているかを確認するために実施されます。
シークレットキーを取得する
ユーザー登録が完了すると、API連携に必要な「APIキー」と「シークレットキー」が発行されます。
APIキーは、どのアプリケーションからの要求かを識別するためのIDのようなものです。一方、シークレットキーは他者に公開しないパスワードのような役割を持ち、APIキーと組み合わせて正規の利用者であることを証明します。
APIキーとシークレットキーは、システム間の認証に用いる非常に重要な情報です。万が一、第三者に漏えいすると不正アクセスの原因となるため、IDやパスワードと同じように厳重に管理することが大切です。
実装を進める
APIキーとシークレットキーの取得後、開発者はAPI提供元が公開している「仕様書」に沿ってプログラミングを進めます。この仕様書には、APIを呼び出す具体的な命令や送受信するデータの形式、エラー発生時の対応方法といった連携に必要な技術的ルールが詳細に記載されています。開発者はこのルールに従い、自社のシステムに連携機能を組み込むためのコードを記述します。
実装後は、テストを実施することが重要です。テスト段階では、データが正しく送受信されるか、エラー処理は適切かなどを入念に検証し、安定した動作を確認します。この検証を経て、API連携は完了です。
API連携の活用事例

API連携は、SNSでのログイン認証やECサイトの在庫管理など、さまざまな場面で活用されています。具体的な事例を知ることで、自社の業務を効率化するヒントが得られるかもしれません。以下で、代表的な4つの活用事例を紹介します。
SNSアカウントによるログイン認証
SNSアカウントを利用したログイン認証は、API連携の代表的な活用例で、「ソーシャルログイン」とも呼ばれます。
ユーザーは、Webサービスやアプリケーションへ新規登録する際に、氏名やメールアドレスといった情報を新たに入力する必要がありません。X(旧Twitter)やGoogleなどの既存アカウントを選択するだけで、簡単にサービス利用を開始できます。
ユーザー側には、複数のID・パスワードを管理する必要がなくなり利便性が向上する、事業者側には、会員登録のハードルが下がり新規ユーザーを獲得しやすくなるというメリットがあります。
ECサイトの在庫管理
ECサイトの運営において、API連携は在庫管理業務を大幅に効率化します。例えば、自社サイトや複数のオンラインモールなど、異なる販売チャネルで商品を展開している場合、APIを通じて各チャネルと在庫管理システムを連携させることが可能です。これにより、どこかのチャネルで商品が一つ売れると、連携している全てのチャネルの在庫情報がリアルタイムで自動的に更新されます。
手作業による更新の手間やタイムラグがなくなるため、在庫切れのまま販売してしまう「売り越し」や、在庫があるのに販売できない「機会損失」を防げます。
経理システムや会計システムの連携
経理システムや会計システムも、API連携によって業務を大幅に効率化できます。例えば、銀行システムのAPIと連携すれば、入出金明細を自動で取得し、会計ソフトに反映させることが可能です。これにより、手作業での明細入力や仕訳作業の手間が省け、入力ミスも防げます。
また、勤怠管理システムと給与計算システムを連携させれば、勤務データに基づいた給与計算が自動で行われます。請求書発行システムと連携して売上データを自動で取り込むなど、定型的な作業を自動化することで、経理担当者は月次決算や分析といった業務に時間を使えるでしょう。
マイナンバーカードによる連携
マイナンバーカードの公的個人認証サービス(JPKI)とAPIを連携させることで、オンライン上で本人確認を行うことも可能です。ユーザーがスマートフォンなどでマイナンバーカードを読み取ると、カードに格納された電子証明書のデータがAPIを通じて事業者のシステムへ安全に送信されます。
この仕組みは、金融機関の口座開設や行政サービスのオンライン申請などで活用されています。事業者側は、郵送による書類のやり取りが不要になり、本人確認業務を効率化できます。ユーザー側も、役所へ出向く手間が省け、迅速に手続きを完了できる点がメリットです。
API連携を活用して業務を効率化しよう!
API連携は、異なるシステムをつなぎ、業務効率化や開発コスト削減を実現する有効な手段です。実装には目的の明確化や適切な手順が重要で、SNSログインから在庫管理まで幅広く活用できます
株式会社SPでは、企画から開発、運用まで一気通貫でAPI連携をサポートし、お客様の課題に適した提案を行います。医療やEC分野などの専門知識を生かし、事業成長を長期的に支援することも可能です。API連携による業務効率化でお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談ください。