
事業の海外展開を考えるうえで、Webサイトの多言語対応は欠かせません。しかし、テキストをただ翻訳しただけでは、
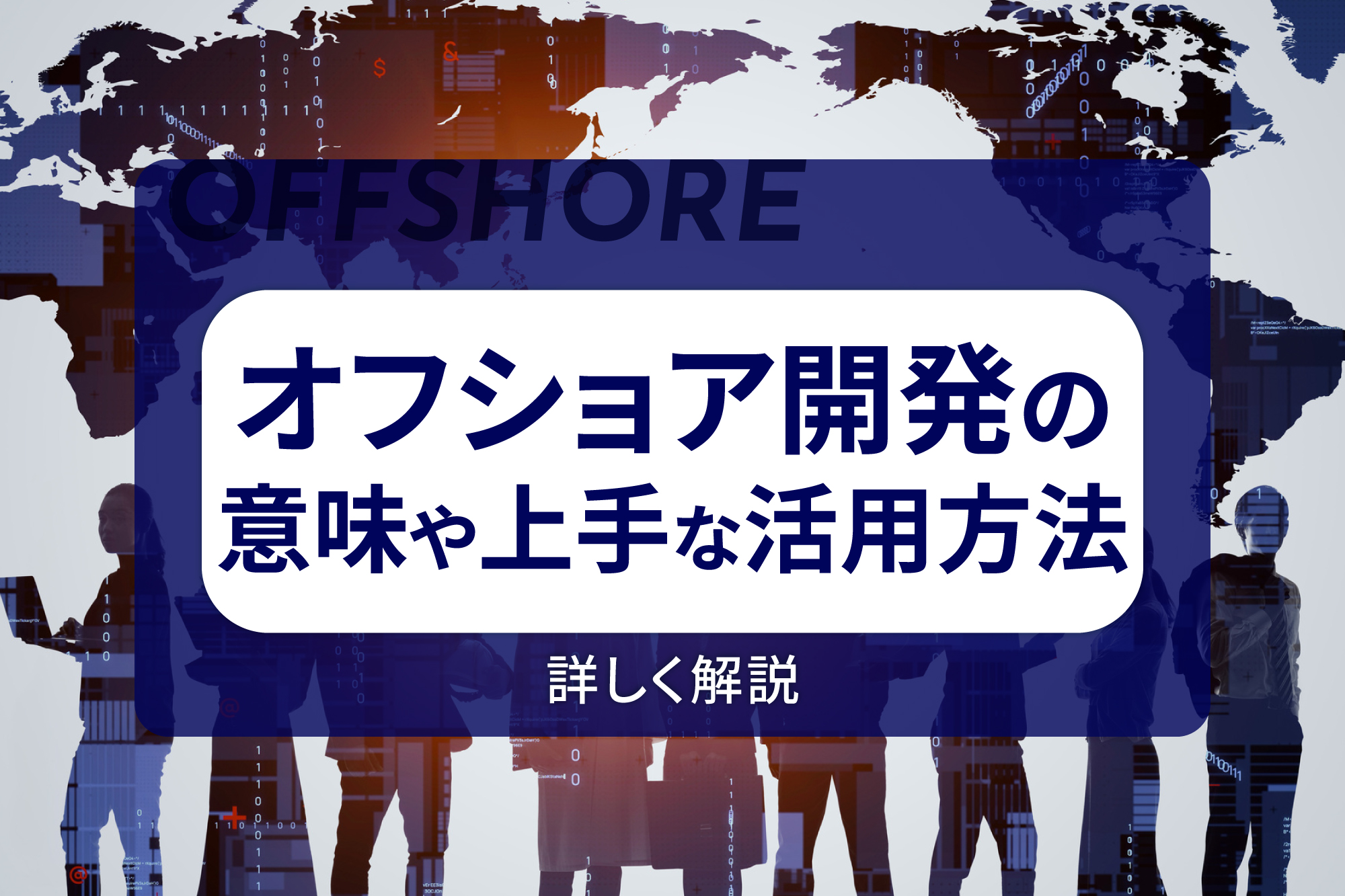
国内のIT人材不足は、年々深刻化しています。エンジニアの人件費も高騰を続けており、システム開発に必要なリソース

オフショア開発は、コスト削減や優秀なIT人材の確保を目的に、多くの企業で検討されています。しかし、実際に導入を
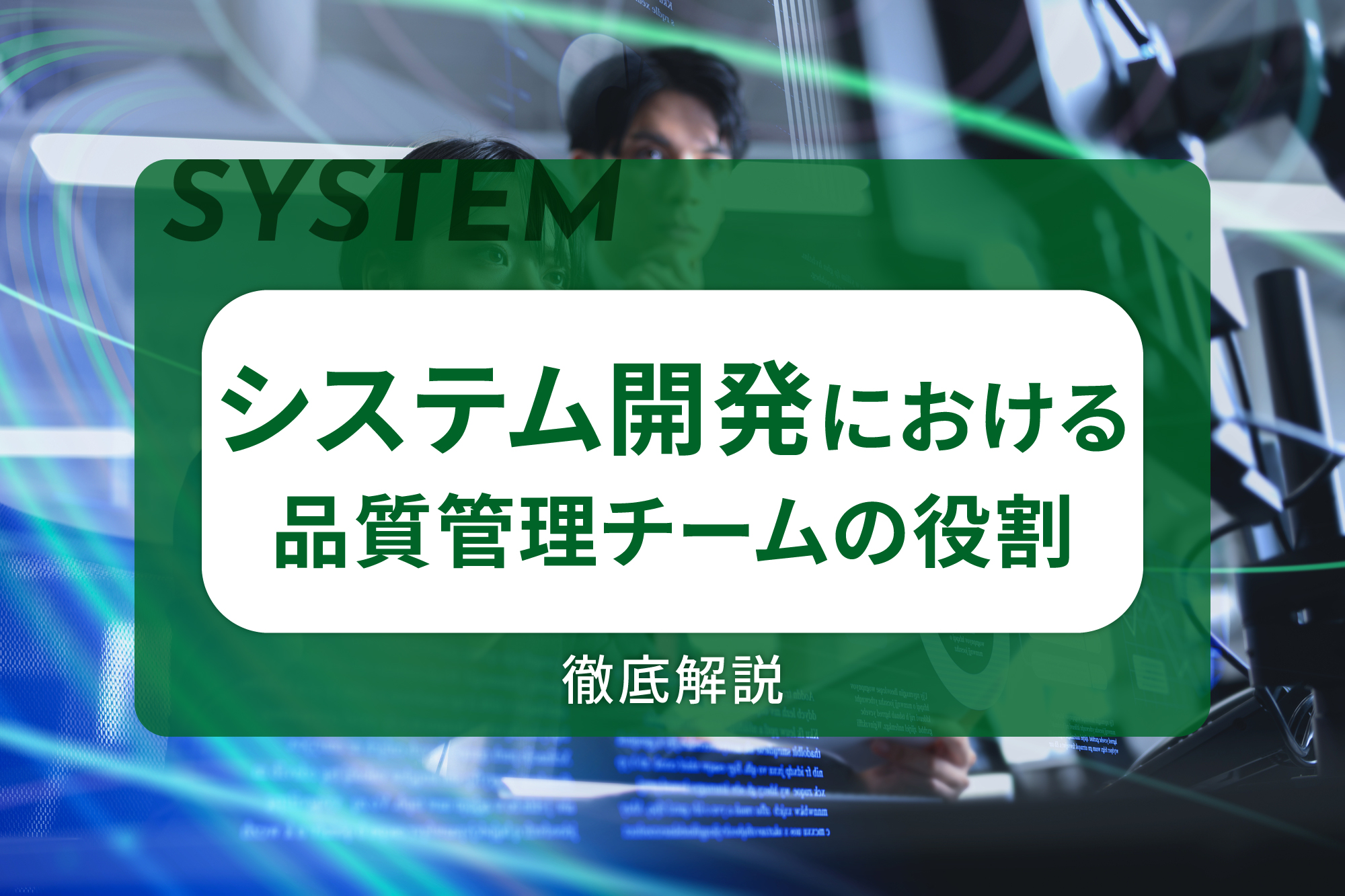
システム開発において、プロダクトの品質はプロジェクトの成果を左右する要素です。しかし、品質管理のノウハウがなく


Copyright © 2024 SP Inc. All Rights Reserved.