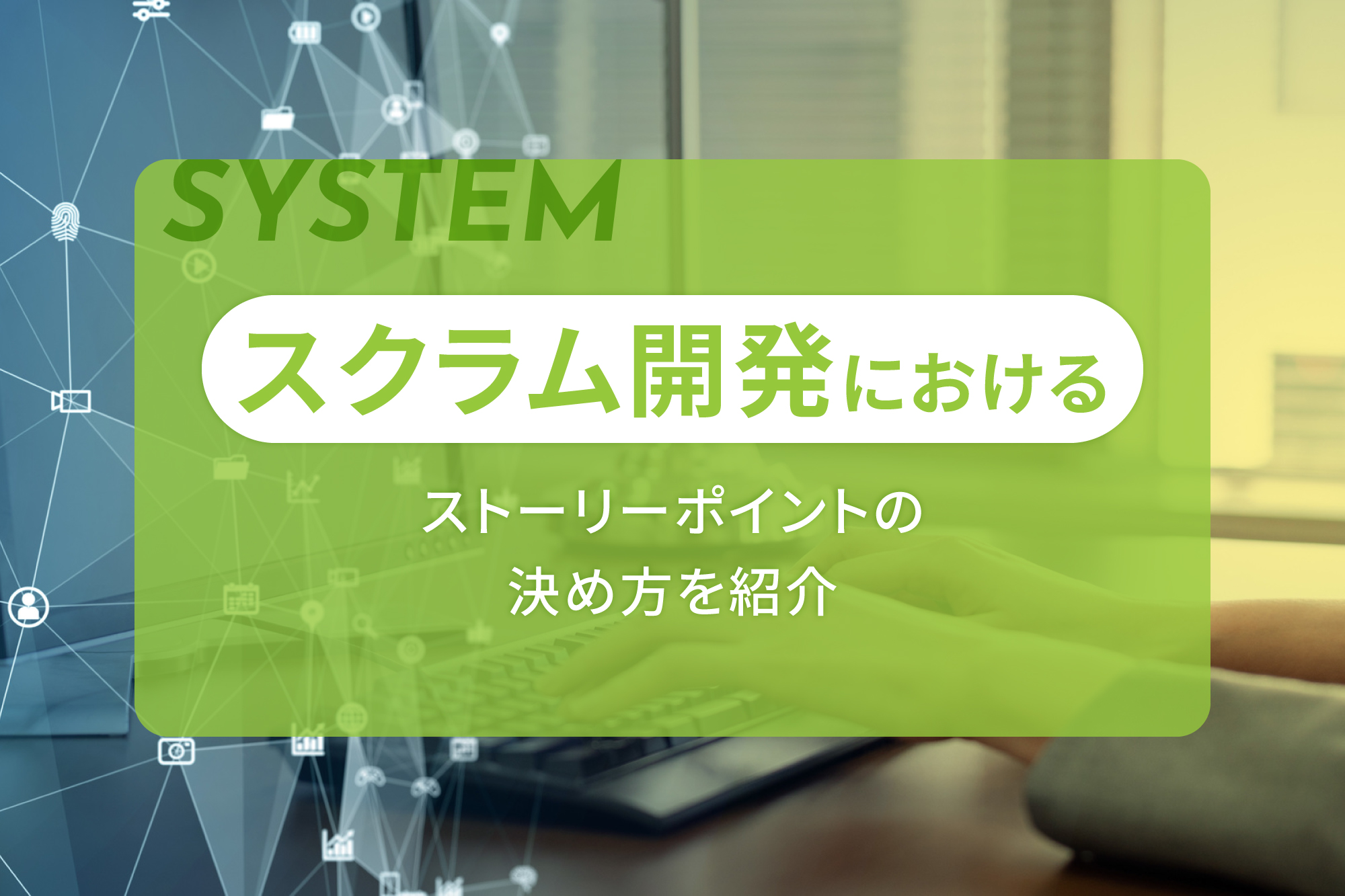
スクラム開発では、スプリントごとにタスクの規模を正確に見積もることがプロジェクトの成否を左右します。しかし、作

紙帳票のデータ化のためにOCRを導入したものの、手書き文字の認識精度が低く、修正作業に追われていませんか。これ

製造業の外観検査や店舗の在庫管理など、物体検出技術の活用が広がっています。しかし、期待した精度が出ずに不良品の

システム開発において、リリース後のトラブルは事業に大きな影響を与えます。「リリースしてみたら、想定外の不具合が


Copyright © 2024 SP Inc. All Rights Reserved.