
はじめに 本記事では、2024年10月に一般ユーザ向けに正式リリースされた、Excel上でPythonを実行で
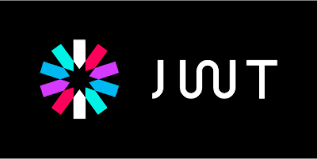
はじめに システムの内部連携のためにJWTトークンによる認証を行う必要があるとのことで、その導入をおこないまし
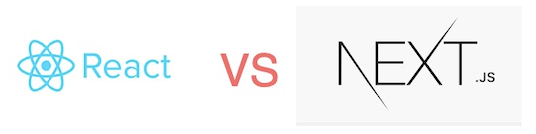
はじめに 開発者なら言わずもがなReactは知っている方がほとんどかと思います。Stateで直感的かつ簡潔に状

はじめに データベースの設計は基本設計の中でもかなり重要な工程です。特にデータの構造によってアプリケーションが


Copyright © 2024 SP Inc. All Rights Reserved.