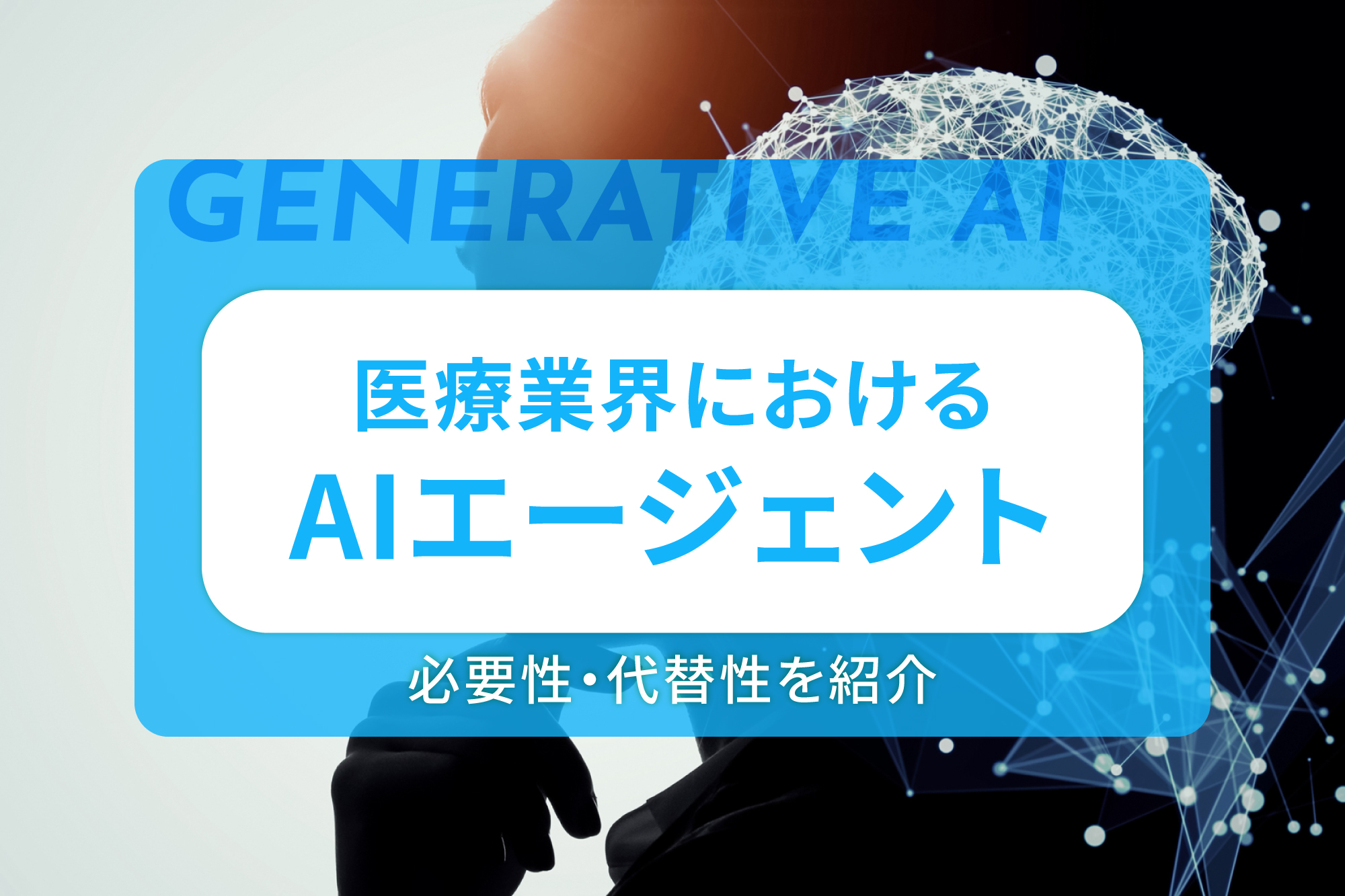
医療業界は、少子高齢化による人手不足や患者数の増加といった課題に直面しています。医療従事者の長時間労働も常態化

多くの企業でAIツールの導入が進む一方、その能力を十分に引き出せていないケースが見られます。特にMicroso

手書きの書類や多様なフォーマットの帳票を扱う業務では、データ入力に多くの時間を要します。手作業による入力ミスや

日本に在留する外国人や訪日客の増加により、医療現場で外国人患者に対応する機会が増えています。しかし、多くの医療


Copyright © 2024 SP Inc. All Rights Reserved.